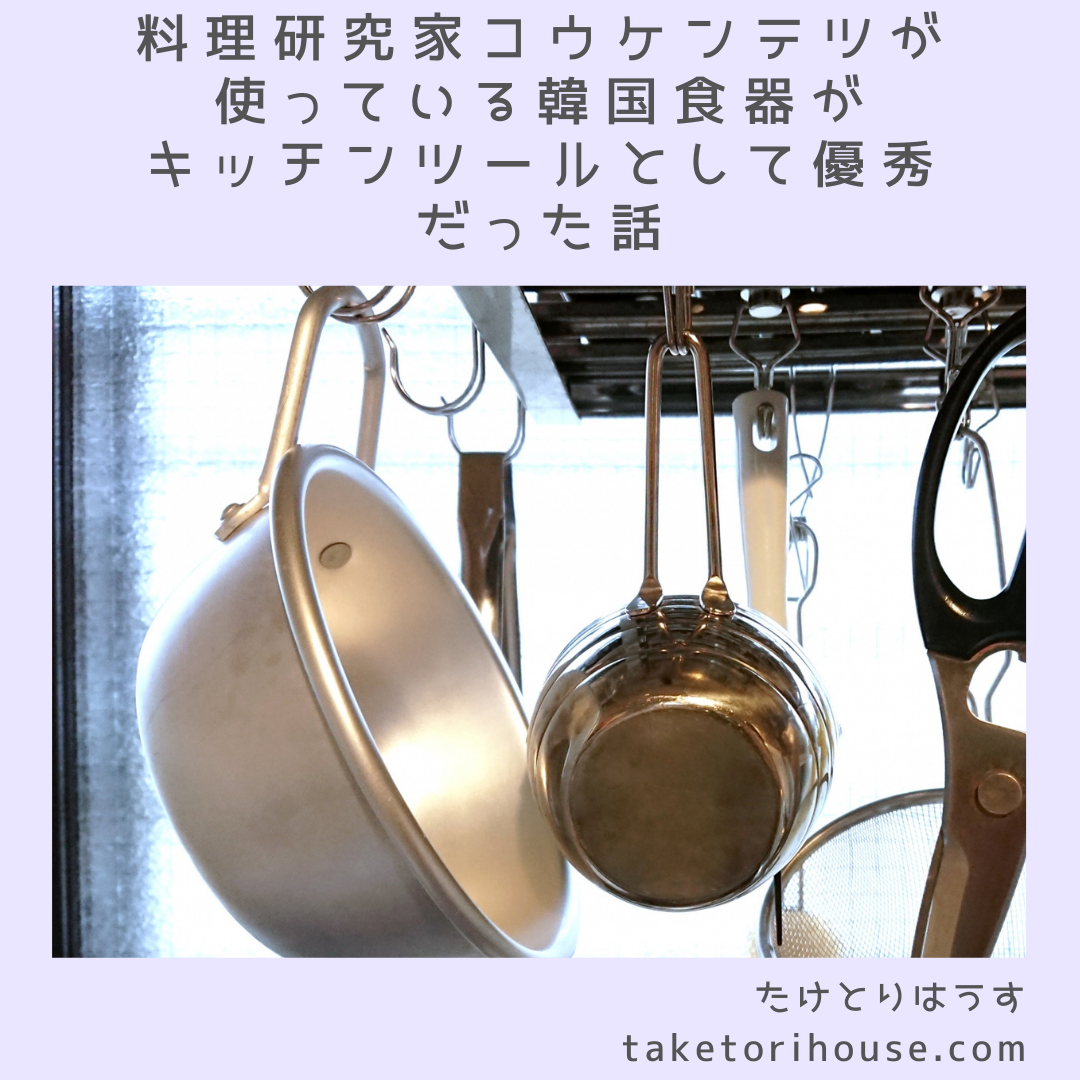八丁味噌とか白味噌とか信州味噌とか日本全国に色々ある味噌。
味噌についてはあまり詳しくなくて、なんとなく料理に使うからレシピに書いてある味噌をスーパーで買ってきて旨いね!と言いながら使っていた私。
でも味噌ってとても興味深い食品なんですね。作り方、材料によってたくさんバリエーションがあり、全国の様々な気候や風土に合わせて味噌の文化が発展し、その味噌の特徴を活かしたメニューがたくさんあります。
今回は味噌の特徴とそれぞれの味噌を活かしたメニューについてご紹介したいと思います。
本当はとても美味しい味噌ラーメンのスープを食べたくて本気で調べたのが始まりです(笑)
それではご紹介スタート
味噌の違いは材料と熟成期間の違いの結果です

味噌は大豆を熟成発酵させた食品です。その大豆を発酵させる元となるのが麹と呼ばれるカビの仲間を穀物や豆類で繁殖させたものを塩と一緒に混ぜて味噌の材料とします。
味噌は色による名前わけもされていて白味噌や赤味噌などと呼ばれています。この色の違いは味噌の熟成期間の違いによって生じます。
長い時間発酵させているとどんどん茶色が濃くなっていきます。これは味噌の中の糖分と旨味成分のアミノ酸などが反応して茶色成分が増加していく結果なのです。
そのため長期熟成の味噌=濃い色の味噌となります。
それぞの特徴について詳しく見ていきましょう。
麹の種類について

麹の種類の分類は麹菌の種類と麹菌を育てる食材で決まります。味噌づくりに使われる麹菌は黄麹と言われる種類。味噌に限らずしょう油やみりん作りなどは黄麹が使われます。
日本酒には白麹、焼酎には黒麹、鰹節にはカツオブシ菌などの麹菌が使われ、発酵食品の担い手として日本食のバリエーションを豊かにする一助となっているのです。
麹に使われる食材の面から見た味噌に使われる麹の分類は3種類。
- 米麹
- 豆麹
- 麦麹
米麹が白味噌、関東人が普通に味噌と言っている茶色の味噌、信州味噌や仙台味噌に使われる麹です。
豆麹は八丁味噌に代表される愛知県周辺で作られている豆味噌の材料となる大豆を原料とする麹の種類です。
麦麹は原料が小麦のもの大麦のものの2種類があり、それぞれ麦味噌の材料として使われます。
最近では塩麹の原料に麦麹を使って料理のバリエーションを増やしている方もいるようです。
味わいは米麹や豆麹に比べて味噌にしたときにあっさりとした仕上がりになります。
麹の量について

麹の量で味噌の口当たりも変化します。麹が多めになると味噌は甘口に、少なめだと大豆の旨味と香りが全面に出た仕上がりになります。
例えば関西でよく食べられている白味噌は米麹の量が乾燥大豆に対して1.5倍から3倍になるのが一般的です。
信州味噌などは乾燥大豆に対して1倍の等量付近が一般的となっています。
さらに仙台味噌などは0.6〜0.8倍の麹量となっており、味わいに地域差がでます。
熟成期間について

熟成期間は色に大きく影響します。熟成期間が短い味噌は白っぽくなり、長い味噌は褐色が濃くなります。
西京味噌に代表される関西地方でよく食べられている白味噌は熟成期間が短く2週間ほどです。
一方、愛知県やその周辺でよく食べられている八丁味噌に代表される豆味噌は赤味噌とよばれ2年以上熟成させることもあります。そのため、味噌の色は濃い褐色となるのです。
味噌の熟成中には炭水化物とアミノ酸類が結合する反応が進みます。この結合した物質が褐色をしていることが長期間熟成した味噌が濃い褐色になる理由です。
塩の量について

味噌には5〜15%の食塩が入っており、その量は発酵期間に関係します。
塩分濃度が高いほうが保存がきき、結果として長期間発酵させることが可能となります。その結果、大豆タンパク質が発酵分解して生じる複雑な旨味が前面に出た味わいとなるのです。これは八丁味噌を代表とした中部地方で食べられている赤味噌の代表的な特徴となっています。
逆に塩分濃度が低い味噌は長期保存ができないため、発酵期間も結果として短くなります。そのため、麹の甘みが前面に出た味わいになるのです。これは関西地方で食べられている西京味噌を代表とした白味噌の特徴です。
味噌の材料と特徴のまとめ

長い歴史を経て塩分濃度、麹の量、どちらが先に決まったかはわかりません。しかし塩分濃度、熟成期間と味噌の色味の関係は必然的に表にまとめたとおりの特徴にまとめられます。
| 代表的な味噌 | 塩分濃度 | 熟成期間 | 味噌の色 | 味わい | |
| 白味噌(西京味噌など) | 低い (5%前後) | 短い (10日前後から) | ベージュ | 麹の甘みが前面に出た味 | |
| 関東で一般に食べる 米味噌 | 中程度 (10%前後) | 中程度 (6-9ヶ月程度) | 褐色 | 甘みと旨味のバランスが とれた味 | |
| 赤味噌(八丁味噌など) | 高い (10-15%) | 長い (1年以上) | 濃い褐色 | 豆の旨味が前面に出た味 |
米がたくさん取れる地域では米麹をたくさん使い、早く食べれるように調整した結果、白味噌が誕生し、大豆が豊富に取れる地域では大豆が多めになるため味噌全体の糖分が少なく長期間の熟成期間が必然的に長くなり、必要に応じて保存ために塩分濃度が高くなったのでしょう。
【PR】手作り味噌セットはいかがですか
- 大豆・麹・塩の必要な材料がセットになっています
- 出来上がりの量も1kgから10kgと必要な量に合わせて購入できます
- 発酵食品についての食育に最適
味噌に合わせてぴったりな料理も多種多様

日本の各地域に広がった味噌の文化、それぞれの地方でその地方にあわせて発展し、それぞれの地域の食材と色々なメニューのバリエーションを展開しています。
それぞれの味噌にぴったりな料理をご紹介していこうとおもいます。
白味噌にピッタリなメニューは?

白味噌にぴったりなメニューは麹の甘みを活かした料理や麹に含まれる酵素の働きを利用した料理が挙げられます。またお酢との相性もバッチリなので酢味噌和えなどの料理にも最適です。
お肉や魚の西京漬

西京漬は白味噌ベースの漬けダレでお肉や魚を漬け込んだ味噌漬けのことをさします。
ざっくり言うと京都の白味噌を西京味噌というので、その味噌を使った味噌漬けを西京漬というのです。米みそを使うと味噌漬けになりますが、また違った風味でこちらもおいしく出来おすすめです。
白味噌にはお肉や魚のタンパク質を旨味成分のアミノ酸などに分解してくれるプロテアーゼをたくさん含む麹がたくさん配合されています。そのため魚やお肉を漬け込むのにぴったりです。
参考のレシピ:【ジップロック活用】さわらの西京漬・味噌漬を自宅で格安かつ簡単に短時間で作るの巻【食器洗い減らし隊】
鶏のむね肉とシメジのからし酢味噌あえ

白味噌にはお酢がよく合います。甘めの味付けにして魚介類やお肉、お好みの野菜とあえる酢味噌あえはさっぱりしてておすすめです。
特にパサつきがちな鶏むね肉とえのきを組み合わせた酢味噌和えはご飯のおかずにもおつまみにもピッタリです。
| 白味噌 | 大さじ2 |
| お酢 | 大さじ1 |
| 砂糖 | 大さじ1 |
| 鶏むね肉 | 1枚(200〜300g) |
| エノキ | 1パック |
| 小ねぎ | お好みで |
材料はからし酢味噌、鶏むね肉、えのきとお好みで小ねぎなどをちらします。味噌は白味噌を使っても美味しいですし、関東や信州で使うような米みそを使っても美味しいです。

作り方はからし酢味噌をつくり、下茹でしひとくちサイズに切った鶏むね肉とえのきとあえ、お皿に盛り付け小ねぎをちらして完成です。
からし酢味噌は自分で作ってもいいし、完成品のチューブ製品を利用しても美味しくできます。
ごはんのおかずにもおつまみにもぴったりです。
赤味噌にぴったりなメニューは?

赤味噌にぴったりな料理は長期間の発酵から生まれる豆の旨さを前面に押し出したメニューがぴったりです。
特に食材にしっかりとした風味がついてるモツ煮やスジ煮などの煮込み料理、しっかりとしたうどんと合わせる味噌煮込みうどんなどがオススメのメニューとなります。
赤味噌で作るモツ煮

赤味噌は味噌そのものの風味や味わいが力強いため、負けない力強さをもった食材との組み合わせがピッタリです。
特におすすめしたいのが赤みそで作るもつ煮です。愛知県の名古屋市周辺では特に赤味噌の代名詞である八丁味噌を使ったもつ煮のことを「どて煮」と呼び、周辺の居酒屋での定番メニューとなっています。
| 豚モツ | 500g |
| こんにゃく | 2枚 |
| ダイコン | 1/4本 |
| ニンジン | 1本 |
| 日本酒 | 150ml |
| みりん | 150ml |
| 水 | 150ml |
| 粉末和風だし | 小さじ2 |
| 砂糖 | 大さじ1 |
| すりおろしニンニク | 小さじ2 |
| すりおろしショウガ | 大さじ1 |
家庭で作る場合はモツを下茹でし、野菜と赤味噌を含む調味料をあわせ煮込んで料理します。煮込みの際は圧力鍋などを使うと時短になるのでおすすめです。
味噌を使った料理は味噌を入れてからグツグツ煮込むことはあまりしませんが、赤味噌をつかったメニューは煮込むことがあります。これは、特徴である強い風味と味は煮込んでも損なわれることがないからです。
味噌煮込みうどん

またもや名古屋地域のメニューのご紹介になってしまいますが、赤味噌がぴったりのメニューといったら味噌煮込みうどんが欠かせません。歯ごたえの良い固めのうどんに負けない強い味をもった赤味噌ベースのダシがおいしいメニューです。
| うどん | 1玉 |
| 鶏もも肉 | 1/3枚(100gくらい) |
| たまご | 1個 |
| ネギ | 1本 |
| しいたけ | 2個 |
| 油揚げ | 1枚 |
| かまぼこ | 3切 |
| 水 | 500ml |
| 粉末和風だし | 小さじ2 |
| 赤味噌 | 大さじ1 |
| 日本酒 | 大さじ1 |
| 砂糖 | 大さじ1/2 |
| 七味唐辛子 | お好みで |
作り方は粉末和風だしを溶かした水に調味料類と赤味噌を加え中火で加熱します。一口大に切った具材を赤味噌のよく効いた出汁に入れていき、次にうどんを投入します。最後に卵をのせ完成です。
うどんは生麺のままいれるのが特徴で、味噌煮込みうどん専用品がおすすめです。
しっかり具材とうどんを煮込むことで赤味噌の力強い味わいが楽しめます。
麦味噌にピッタリなメニューは?

麦味噌は主に九州や中国地方で食べられる味噌です。もともと麦を盛んに栽培していたため、味噌作りに麦麹を用いるようになりました。温暖な土地柄もあり、味噌の発酵時間は短めです。塩分濃度は低いのが一般的です。麦麹の量も比較的多めなこともあり、味わいは甘みが強めであっさりとした風味が特徴となっています。
麦味噌に合うメニューは多めに入っている麦麹の酵素を活かした肉料理やあっさりとした味わいがぴったりな宮崎の冷汁などが挙げられます。
豚肉とナスの味噌炒め

麹を多めに配合する麦味噌は酵素のちからが期待でき、肉料理にぴったりです。また、米味噌に比べて爽やかな味わいは夏野菜にもよく合います。
特におすすめなのが豚肉とナスの味噌炒めで、優しい麦味噌の香りがご飯との相性バッチリです。
| 豚バラ薄切り | 200g |
| なす | 3本 |
| すりおろしニンニク | 小さじ1/2 |
| すりおろしショウガ | 小さじ1/2 |
| サラダ油 | 大さじ2 |
| 麦味噌 | 大さじ2 |
| 砂糖 | 大さじ1 |
| しょう油 | 大さじ1 |
| みりん | 大さじ1 |
| 日本酒 | 大さじ1 |
ナスと豚肉の味噌炒めは切ったナスと豚の薄切りをニンニクとショウガで香り付けしたサラダ油で炒め、麦味噌、しょう油、みりん、日本酒を加えてさっと完成です。
お好みでごまを入れたり、豆板醤を少し入れたりしてピリ辛に仕上げても美味しくいただけます。とてもご飯がすすむ味付けとなっています。
冷や汁

次に麦味噌メニューとしておすすめしたいのが宮崎県のソウルフード「冷や汁」です。冷や汁とはアジの干物や鯛の塩焼きのほぐし身と麦味噌をあわせた冷製の味噌汁みたいなメニューです。
食欲のなくなる夏の暑い時期にも無理なく食べられる郷土料理となっています。
日本各地に同様の料理があり、九州各地や関東地方でもご当地グルメとして知られています。

ちなみに関東地方の冷や汁は埼玉県のB級グルメ「すったて」として知られてうどんのつけ汁として親しまれています。これは米みそを材料につかう料理です。
| うどん | 2人前 |
| 水 | 500ml |
| 粉末和風だし | 小さじ2 |
| 味噌 | おたま1 |
| 砂糖 | 小さじ1/2 |
| しょう油 | 小さじ1 |
| みりん | 小さじ1 |
| すりごま | 大さじ1 |
| アジの塩焼きほぐし身 | 1匹分 |
| 木綿豆腐 | 1丁 |
| きゅうり | 1本 |
| 大葉 | 2枚 |
| みょうが | 1本 |
我が家では宮崎の郷土料理の冷や汁をうどんのつけ汁にして食べます。宮崎風の冷や汁には白身魚やアジのほぐし身が入るのでとっても味わい深いです。
作り方は粉末和風だしを水に溶かし、味噌、しょう油、砂糖、みりん、すりごま、アジの塩焼きのほぐし身とさいの目に切った木綿豆腐を入れ加熱します。沸騰直前まで加熱したら火を止め、薄切りにしたきゅうりを加えて粗熱をとり冷蔵庫で冷やします。
うどんを茹で、流水で冷まし、冷蔵庫で冷えた冷や汁をうどんにかけます。お好みでしそやみょうがを添えれば完成です。
まとめ
- 疑問に思ってた様々な味噌について特徴をまとめてみました。調べ出ると味噌は地域の風土に根ざしたバリエーション豊かな調味料でした。
- 味噌づくりのための多彩なキットがネットで販売しています。自分の好みに合わせた味噌づくりにチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
- 味噌は今、ブームになっている発酵食品の一つです。味噌作りを通じて発酵食品への理解を深めてはどうでしょうか。味噌の手作りを通じておこ様の食育や伝統文化への理解を深めるイベントに好適です。